前回の記事では、静電エネルギーの意味と、2個の電荷によるエネルギーからN個の電荷によるエネルギーへの拡張について説明しました。ここでは、N個の電荷によるエネルギーを異なる形へと変えていきます。
電荷間のエネルギーによる表現
今回の出発点はN個の電荷によるエネルギーです。
\(U = \displaystyle \dfrac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \dfrac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}\)
ただし、\(i=j\)は除く
これは、N個の電荷間のエネルギーを、あらゆる組み合わせで計算して合算する式です。1/2がついているのは、同じエネルギーを2回ずつ計算するから、1回ずつの計算結果にするためです。
さて、ここで、ふたつある\(\sum\)を分離してみます。具体的には、\(\displaystyle \sum_{i=1}^{N} q_i\)と\(\displaystyle \sum_{j=1}^{N} \dfrac{q_j}{4\pi \epsilon_0 r_{ij}}\)に分けます。後者は、\(j\)が1番めからN番目までの\(q_j\)の電位の和を示しています。ここからは、静電場における電位とは何か、について理解しておくことが必要です。
静電場における電位とは
電位とは、静電場の中における1Cの点電荷(単位電荷)の位置エネルギーです。すなわち、電位ゼロの無限遠から、別の点電荷Qとの間にはたらくクーロン力に逆らって、単位電荷を電荷Qへ近づけていったときの仕事に相当します。
最もシンプルな1次元のケースでこの仕事量を計算してみます。無限遠(電位ゼロ)にある電荷qを、電荷Qへクーロン力に逆らってゆっくり近づけることを考えます。まず、ふたつの電荷Qとqの間に働くクーロン力の大きさはクーロンの法則により、
\(F = \displaystyle \dfrac{qQ}{4\pi \epsilon_0 r^2}\)
このクーロン力を距離で積分したものが仕事Wです。距離\(r_1\)から\(r_2\)まで積分すると仮定すると、
\(W = \displaystyle -\int_{r_1}^{r_2} F dr = -\int_{r_1}^{r_2} \dfrac{qQ}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr\)
電荷qは電荷Qから仕事をされる(電荷間にはたらくクーロン力と反対の力を電荷qへはたらかせる)ので、マイナスが付いています。計算を続けると、
\( W = \displaystyle \dfrac{qQ}{4\pi \epsilon_0} \left[\dfrac{1}{r}\right]_{r_1}^{r_2}\)
\( = \dfrac{qQ}{4\pi \epsilon_0} \displaystyle \left(\dfrac{1}{r_2} – \dfrac{1}{r_1}\right)\)
\(r_1\)に無限遠(∞)を、\(r_2\)に最終的な電荷qとQの距離rを代入すると、最終的に導かれる仕事は次の式で表されます。
\(W = \dfrac{qQ}{4\pi \epsilon_0 r}\)
これが、電荷qの位置エネルギーになります。単位電荷の場合はq=1を代入すると、電位Vになります。
\(V =\dfrac{Q}{4\pi \epsilon_0 r}\)
考える静電場が2次元や3次元になると、ベクトルで表したりと表現が変わっていきますが、基本的な考え方は変わりません。
電荷密度と電位による表現へ
電荷\(q_i\)の位置の電位を(V_i(\vec{x_i}))で表すと、最初の式は次のように変わります。
\(U = \displaystyle \dfrac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i V_i(\vec{x_i})\)
ただし、電位\(V_i (\vec{x_i})\)は、\(q_i\)が作る電位を除く
これは、電荷qと電位Vの仕事を表す公式U=qVをN個の電荷について計算して合計するものです。また、電位を表す部分はベクトル表記になっています。さっきまでは、電荷\(q_i\)の位置は他の電荷との相対的な距離(r)で表されていたので、電荷間の距離があれば、エネルギーを表現することができました。しかし、電位で表すことになったため、任意の電荷の位置の電位であることを表す必要があるため、電荷\(q_i\)の位置を示すのにベクトル表記を用いているわけです。
ここで、式から\(\sum\)を省くことを考えます。この式のままでは、それぞれの電荷ごとにエネルギーを計算してから合計する必要があります。これでは計算が不便です。どうせ和を計算するのであれば、積分の形のほうが便利です。そこで、考え方を変えます。ここまでは、電荷を個別に区切っていました。具体的には、ひとつひとつ電荷のエネルギーを計算し、すべての電荷のエネルギーを合計していました。ここからは、電荷ではなく、空間を区切ります。
特殊なケースを除くと、電荷は通常は連続的に分布していると考えられます。この場合、個々に区切った空間に含まれる電荷量は、(電荷密度✕個々に区切った体積)で表すことができます。この段階では、まだ区切った体積の中の電荷ごとに電位が異なります。そこで、区切る体積をどんどん小さく、区切った体積の中の電荷ごとに電位が変わることがないようにしていきます。つまり、区切る体積をゼロ(極限)に持っていくわけです。位置\(\vec{x}\)における電荷密度を\(\rho (\vec{x})\)、電位を\(V(\vec{x})\)、極限の微小体積を\(dxdydz\)で表すとすると、微小体積中の電荷のエネルギーは、この3つをかけ合わせたものになります。また、ここのエネルギーの和は、極限では積分に置き換えることができるので、これらでエネルギーの式の各要素を置き換えます。
\(U = \displaystyle \dfrac{1}{2} \int \rho (\vec{x}) V(\vec{x}) dxdydz\)
これが、エネルギーを電荷密度と電位により表現した式です。
次回以降、式の変換を進めていきます。
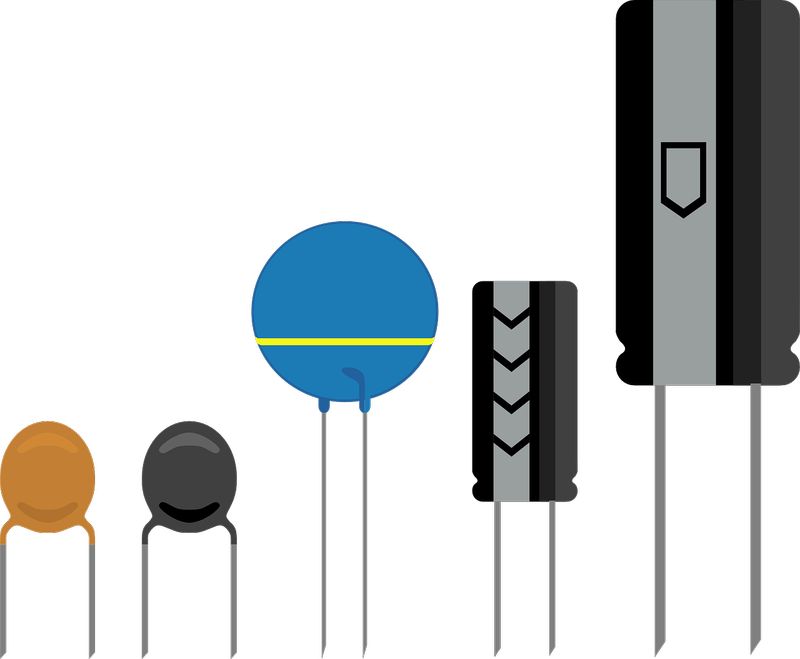

コメント