別の記事では、静電エネルギーは電場が持つことを示しました。実際に、エネルギーを示す式は変数としては電場を含むのみで、電場が決まれば体積積分することでエネルギー量が確定する形になっていました。しかし、式を導出する過程では、さまざまな式を変形したり代入したりしており、ただ式をこねくり回しただけ、との感じもします。そこで、今回は、電荷間の静電エネルギーが、電場が持つ形になるまでを、順を追っていきます。
はじめに
なぜこのような面倒なことをするのか。それは、式をいじるだけでは何をやっているのかイメージできず気持ち悪い、と感じる人の理解の助けにするためです。世の中には、式をいじって目的を達成して満足できる人もいれば、それだけでは何をやっているのかわからず、気持ち悪さを感じる人もいます。私は完全に後者なので、過程を順を追って行かないと理解というか満足できず、勉強が先に進まなくなります。イメージできないと理解できた気分になれないんですね。つくづく私は物理とは相性が悪いな、と思います。
物理ではひとつのことを表現するのにさまざまな形があり、さまざまな式を組み合わせることで新しいことを表現することができるようになります。これはこれで便利だと思います。しかし、初学者にとっては、これは結構きついんですね。渡しの場合、説明を聞いたときは、式の変形の話なので分かった気になります。ただ、時間を置いて見直すと、式が次々に変形してはいくものの、なぜそうできるのか、その内容をどのようにイメージすればよいのかがわからず、わからないまま記憶から消えて行くことが多い人もいると思います。
本題に戻ります。静電場では、電荷がなければ電場も生まれません。したがって、電場が持つ形で表現された静電エネルギーは、もともとは電荷が持つエネルギーに由来するといえます。では、なぜ静電エネルギーはこのようにさまざまな形で表現されるのか。それは、それぞれの表現で用いられる要素どうしがお互いに関連しあっているから、といえます。したがって、その関連を追っていくことで、電荷が持つエネルギーが、なぜ電場が持つエネルギーに形を変えていくのかを理解できるようになると思います。
出発点と到達点
まず、出発点と到達点となる式を確認します。出発点は、2個の電荷が持つエネルギーです。真空中の平行平板コンデンサの、最もシンプルな形です。
\(U = \dfrac{Qq}{4\pi \epsilon_0 r}\)
ここで、\(U\)はエネルギー、\(Q\)と\(q\)は点電荷、\(\epsilon_0\)は真空の誘電率、\(r\)は点電荷\(Q\)と\(q\)の間の距離です。この式を、最終的に電場のみの式に持っていきます。
\(U=\dfrac{\epsilon_0}{2} \displaystyle \int \left| \vec{E}\right|^2 d^3 \vec{x}\)
ここで、\(E\)が電場です。
式の変換の流れ
式の変換の流れは下に示すとおりです。
2個の電荷が持つエネルギーとして表現
↓
N個の電荷の集合体が持つ位置エネルギーとして表現
↓
電荷と電位での表現
↓
電荷密度と電位で表現
↓
電場と電位で表現
↓
電場のみで表現
そもそもエネルギーとは?
力学におけるエネルギーとは仕事をする能力のことです。仕事とは、物体に加わる力と移動距離の積です。これを静電場に置き換えると、エネルギーは電荷の位置エネルギーで電荷と電位の積で表され、仕事は電荷に電場に逆らう力を加えて移動させる(電荷が仕事をされる場合)ことに相当します。すなわち、電場に逆らう力を電荷に加えて移動させると、その間に加え続けた力が電荷にエネルギーとして蓄積されると考えることができます。
次回以降、具体的な式の変換を示していきます。
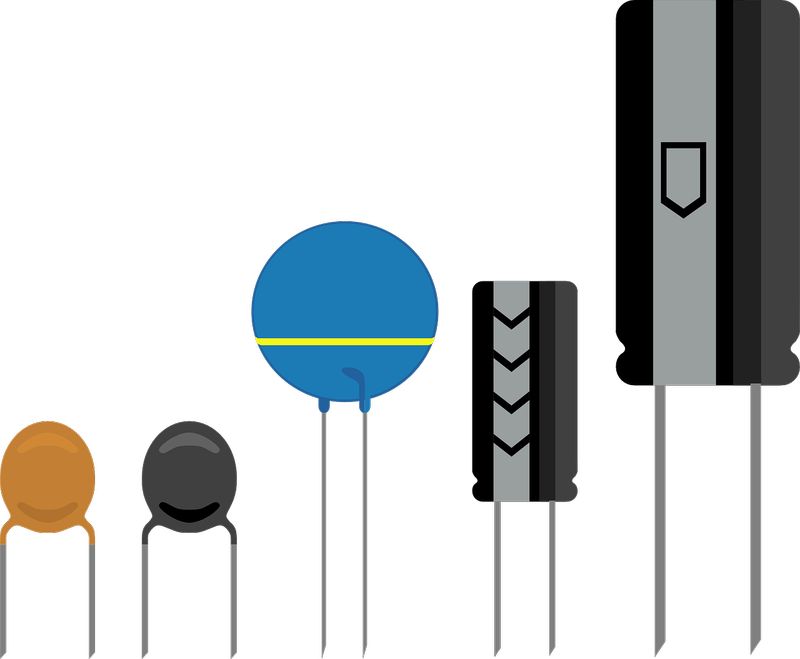

コメント