コンデンサの理論で頻出する関係式が4つあります。そのうちのひとつが「電気量と電圧の比例関係」です。この関係を計算を通して説明します。
コンデンサが蓄えることができる電気量
コンデンサが蓄えることができる電気量は、次のシンプルな式で表されます。
\(Q=CV\)
コンデンサが蓄える電気量と電圧は比例関係にあり、その比例定数は\(C\)(静電容量または電気容量)です。電気量は、コンデンサに印加された電圧とコンデンサの静電容量の積で表されます。この式は、静電容量の定義を表す式でもあります。
より具体的に表現すると、「ふたつの導体があり、それぞれの導体が同じ量で反対符号の電荷(\(+Q\), \(-Q\))で帯電しているとし、これらふたつの導体の間に電位差(\(V\))があるとする。このとき、静電容量を\(C\)とすると、\(Q=CV\)の関係が成り立つ。」となります。
さて、高校の物理の授業でもこの公式は習いますが、そこで出てきたコンデンサの形状は、ほぼ必ずと行っていいほど平行平板コンデンサです。それは、理想的なコンデンサに非常に近く、\(Q=CV\)がシンプルに成立し、また、絵を見て直感的に理解しやすいからです。
平行平板コンデンサを用いて説明する際は、暗黙の了解として、極板どうしの距離が非常に小さく、面積が非常に大きいと仮定しています。極板の端部では極板間の電気力線が極板外に向かって湾曲しますが、この仮定によって、すべての電気力線が極板に対して垂直であるとみなすことができるようになるからです。
では、極板が任意の形状の場合はどうでしょうか? 任意の形状でも\(Q=CV\)の関係は成立します。このことを示すために、段階を踏んでいきます。
- ひとつの導体の場合について考える
- 1の考え方をふたつの導体の場合に適用する。
以下では、極板のように電気伝導性が高い物質を導体と呼びます。電磁気学において、導体とは内部に存在する電荷が自由に移動できるような物質で、以下の性質を持つといえます。
- 導体内部の電位は常に一定である。\(E=-grad V\)より、内部の電場も常に0(ゼロ)である。
- 導体表面の電場の向きは導体表面に垂直で、その大きさは、導体表面の電荷密度\(\sigma\)と電気定数\(\epsilon_0\)により、\(E=\dfrac{\sigma}{\epsilon_0}\)である。
- 導体内部に電荷は存在せず、表面のみに現れる。
- 孤立した導体の表面に現れる電荷の総和は0である。
ひとつの導体の場合
例として、半径\(a\)の球状導体について、電荷と電位の関係を考えます。この導体球表面に電荷\(Q\)が一様に分布すると、その表面電荷密度\(\sigma\)と表面の電場\(E\)は以下の式で表されます。導体球表面の電場は、導体球中心を原点とした場合に径方向の成分のみを持ちます。
\(\sigma = \dfrac{Q}{4\pi a^2}\)
\(E=\dfrac{Q}{4\pi \epsilon_0 a^2}\)
導体球中心を原点とした場合の、半径\(r=a\)の導体球表面と、その外部の半径\(R\)の球面を貫く電気力線の本数は\(Q\)で同じです。ガウスの法則から、このときの電束密度\(D(r)\)は、\(r≧a\)に対して、
\(D(r)=\dfrac{Q}{4\pi r^2}\)
となります。真空のような線型な媒質の場合、電場と電束密度の関係は\(\vec{E}=\dfrac{1}{\epsilon_0}\vec{D}\)であるから、
\(E(r)=\dfrac{1}{\epsilon_0}D(r) = \dfrac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}\)
となります。また、電位が定義できるのは、いま考えている点すべてで\(rot\vec{E}=0\)であり、電場\(E\)と電位\(\phi\)の関係は\(\vec{E}=-grad \phi\)であるから、
\(E(r) = -grad \phi(r) = – \dfrac{\partial\phi(r)}{\partial r}\)
となります。この両辺を積分すると、積分定数を\(C\)として、
\(\phi(r) = \dfrac{Q}{4\pi \epsilon_0 r} + C\)
となります。境界条件は\(r=\infty\)のとき\(\phi=0\)なので、\(C=0\)です。したがって、
\(\phi(r) = \dfrac{Q}{4\pi \epsilon_0 r}\)
です。この関係は、\(r≧a\)に対して成立します。無限遠での電位を0とすると、この導体球の表面での電位は、
\(\phi(a) = \dfrac{Q}{4\pi \epsilon_0 a}\)
となります。この式において、電位と電荷以外はすべて定数なので、\(4\pi \epsilon_0 a = C\)、電位を\(V\)とおくと、\(Q=CV\)となります。つまり、導体がひとつだけ存在する場合、無限遠の電位を0とおくと、\(Q=CV\)が成立します。
この式は、電位差が\(1V\)増加すると電荷量が\(C\)(静電容量)だけ増加することを示します。この例では、静電容量は半径に比例するので、半径の増加分だけ、同じ電位差を発生させた場合の導体球表面の電荷増加量も増えます。逆に、導体球の半径を固定すると、導体球表面に多くの電荷量を発生させると、その分だけ導体球表面の電位も増加します。
この導体球の例では、電荷は導体表面にのみ存在し、導体表面の電場は導体表面に垂直であるから、導体表面の電位はどの位置でも等しいことを利用しています。この導体の性質には導体の形状や寸法は無関係なので、導体表面の形状が球面とは異なっても、導体表面の電位はどの位置でも等しいといえます。このことから、導体球でなくても、孤立した導体では一般的に\(Q=CV\)が成立します。
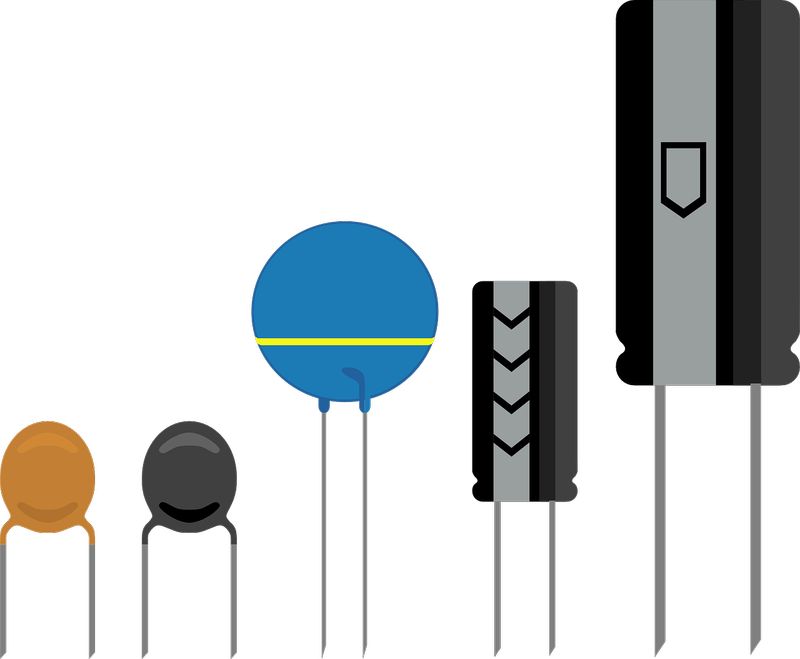

コメント